「家相が悪いと精神病になる」と聞いたら、不安になってしまいませんか?
実際、住環境が暗い、風通しが悪い、動線が不便などの要因によってストレスが高まることはあります。
しかし、家相そのものがすべての原因ではありません。
この記事では、家相とメンタルヘルスの関係や、具体的な改善策をご紹介します。
家相と精神病の関係について気になっている方はぜひ参考にしてください。
精神病になる家相とは?その背景と現象について解説
具体例を紹介する前に、家相がメンタルヘルスに及ぼす主な影響と風水や家相と精神的負担の原因について解説します。
 管理人
管理人へー、そうなんだ!ってのが理解できるはずです!
家相がメンタルヘルスに及ぼす主な影響
家相とメンタルヘルスの関係は、科学的に完全に証明されているわけではありません。
しかし、暗く狭い環境や換気が悪い住空間に長時間いると、気分の落ち込みや不安感が増幅しやすいと指摘されることがあります。また、部屋の配置が複雑すぎたり、収納が不十分で散らかりやすい構造だと、ストレスが溜まりやすいはずです。
こうした住環境からくる心理的負担は、いわゆる「家相が悪い」とされる要因と結びつけられ、結果として気持ちが沈みやすくなり、うつ状態や不安障害につながるケースがあるとも考えられています。
風水や伝承が語る精神的負担の原因
古くから伝わる風水や家相の考え方では、家の方角や間取りが運気だけでなく、精神状態にも影響を与えるとされています。例えば、「鬼門」とされる北東や南西に寝室や玄関があると不調を招くといった伝承は、住む人に対して先入観や不安感を植え付けることがあります。
さらに、その不安が大きくなると、ちょっとした物音や風通しの悪さなどが「何か悪い兆候かもしれない」と感じられ、結果として気持ちがふさぎ込むようになる場合もあるのです。
実際には科学的根拠より心理的要素が強い部分も多く、こうした負担が重なることで「精神病になる家相」との結びつきが語られることがあります。
精神病になる家相の具体例と対策7選
ここからは、精神病になる家相の具体例を紹介します。
これは必ずしも精神病になる家相とは限りません。むしろ、不安に思う家相くらいに思ってもらうと読み進めやすいかなと思います。



ここでは具体例を7つ紹介します。当てはまるものがあればぜひ対策してみて!
1.日当たりの悪い間取り
日光は人の体内リズムを整え、セロトニンの分泌を促す重要な要素です。部屋が北向きばかりであったり、窓が小さく外光がほとんど差し込まない家相の場合、気分が沈みがちになり、鬱々とした状態に陥りやすいとされています。
対策としては、まずカーテンや家具の配置を工夫し、できるだけ自然光を取り込むことが大切です。人工照明も昼白色系の明るいものを用いて、昼夜のメリハリをつけるようにしましょう。また、観葉植物を置くなどして室内環境に“生きた”要素を加えることで、視覚的にもリラックス効果を得られます。
・できるだけ自然光を取り込むために、カーテン・家具などの配置を工夫する
・照明は昼白色系の明るいものにする
・観葉植物などで「生きた要素」を加える
2. 間取りや動線がストレスを生むケース
廊下が狭く曲がりくねっている、部屋が入り組んでいる、家族の生活導線が交錯しやすいなど、日常動線に無理がある家相は、知らず知らずのうちにストレスを増幅させる原因となります。
たとえば、キッチンから洗濯機への移動が遠かったり、寝室がリビングを必ず通らないといけない位置にある場合など、生活音や往来に気を遣うことで精神的な疲労が溜まるはずです。
対策としては家具の配置やパーテーションの利用で動線をシンプルにするとともに、ストレスのもととなる“ぶつかりやすい場所”を減らす工夫が求められます。
・人が動くであろう動線はごちゃごちゃしないようにすると吉
3. 水回りの位置や清潔感に注意
トイレや浴室、キッチンなどの水回りは、家の中でも特に衛生面と密接に関わっています。
カビや汚れが溜まりやすい配置だと、見た目やにおいに対する不快感が募り、精神的に落ち着かない状態を引き起こすことがあります。水回りが暗くて湿気がこもりやすい場合は、換気扇や窓を活用してこまめに換気することが重要です。
さらに、清掃を習慣づけたり、防カビグッズや除湿グッズを使うなど、小さな工夫の積み重ねで清潔感を保てば、不安や不快感を和らげることができます。こうしたポイントを意識するだけでも、家相による悪影響を軽減できる可能性があります。
・水と家相は直結するので、台所やトイレ、ふろ場などの水場は整理整頓を心がけよう
・防カビグッズ、防湿グッズなどを導入する
4. 収納不足と散らかりがもたらすストレス
収納スペースが不足している家相は、生活必需品や衣類を整理しきれず、部屋が常に散らかった状態になりがちです。ものがあふれる空間では、必要な物が見つからずにイライラしたり、視界にゴチャゴチャしたものが入ることで落ち着かない気分を招いたりします。
さらに、散らかった部屋にいると「片付けなきゃ」というプレッシャーが常に頭にこびりつき、精神的な余裕が持てなくなることも少なくありません。
対策としては、まず“今の自分に本当に必要な物”を見極め、不要なものを積極的に処分・リサイクルすることが大切です。また、押入れやクローゼットだけでなく、壁面収納やベッド下収納などを活用する工夫も効果的。
収納家具は高さや奥行きに注意し、取り出しやすい構造にしておくと、片付けのモチベーションが下がりにくくなります。こまめな整理整頓や、生活動線をふさがない収納計画を心がけることで、不安やストレスを大幅に軽減できるでしょう。
・収納しきれないものが溢れている状態は、散らかっているのと同じこと。しっかりと整理整頓しよう。
・収納上手になるためには片付けやすさも大事。
5. 隣家との距離や騒音のストレス
家相は建物の内部だけでなく、敷地や近隣との位置関係にも影響を及ぼします。隣家との距離が極端に近い場合、プライバシーが保ちにくいだけでなく、騒音や視線が気になって神経をすり減らすことがあります。
特に寝室の窓が隣家のリビングに面していたり、道路に面していることで夜中に車の音が響くなどの状況では、安眠やリラックスが阻害されやすくなります。
対策としては、防音カーテンや窓ガラスを導入して音の侵入を軽減する、庭木やフェンスを活用して視線を遮るなどが挙げられます。バルコニーや玄関まわりに植栽を取り入れるだけでも、緑が心を和ませてくれる効果が期待できるでしょう。
もし物理的に改善が難しい場合には、耳栓やホワイトノイズマシンなどを利用して、睡眠環境の質を上げる工夫もおすすめです。
・近くに工場がある、電車が通っているなどの騒音問題も家相的にはNGなので、防音対策はおすすめ
6. 玄関の配置と“気”の流れがもたらす不安
風水や家相では、玄関は“気”が入ってくる重要なポイントとされています。玄関が狭すぎたり、照明が暗くて陰気な雰囲気だと、家に入ってすぐに閉塞感やネガティブな印象を抱きやすくなります。
また、玄関ドアを開けた正面に階段やトイレの扉があると運気を逃すという説もあり、実際に「なんとなく落ち着かない」「人を招きづらい」と感じる方も多いようです。
対策としては、まず玄関にできるだけ自然光や明るい照明を取り入れ、清潔感を保つことを心がけましょう。玄関マットや観葉植物などを置くと、空間に彩りが加わり、“気”の流れが良くなるとされます。
靴や傘などを放置せず、スッキリ片付けることで玄関の印象は劇的に変わります。さらに、もし配置の変更が可能なら、玄関を開けたときに真正面に壁や階段などがこないよう工夫すると、入ってきた“気”が家全体に循環しやすくなるともいわれています。
あくまで風水の考え方の一つではありますが、気持ちよく出入りできる環境づくりは、日常のストレス軽減にもつながります。



玄関の家相は重要なので、詳しくは以下の記事をチェック!


7. 家族のコミュニケーション不足を招く間取りと対策
家族が集まるリビングやダイニングの位置関係が悪く、個々の部屋にこもりがちになる家相は、コミュニケーションの減少につながりやすいです。
たとえば、リビングを通らずに各部屋へ行ける間取りや、廊下の構造上の問題で家族が顔を合わせる機会が少なくなる配置だと、自然と会話が減り、人とのつながりが希薄に感じられるようになります。こうした孤立感や疎外感は、ときには不安や精神的負担の増大につながるケースも見受けられます。
対策としては、まず家族の動線がリビングやダイニングを中心に通るような配置を意識してみましょう。家具の配置を変えるだけでも、家族が集まりやすくなるスペースを演出できます。
また、リビングや共有スペースの照明を工夫して明るい雰囲気を作り、自然とそこに集まりたくなる空気感を演出するのも効果的です。さらに、家族それぞれが過ごしやすい個室を確保しつつも、パーテーションの活用やドアをオープンにしやすい工夫を取り入れれば、適度なプライバシーを保ちながらもコミュニケーションを促進できます。
とくに子育て世代の場合は、小さなお子さんの様子を見守りつつ家事ができるようにするなど、家族間の会話と安全性を両立できる間取りを心がけることが、精神的な安心感にもつながります。
・家族がくつろげるリビング環境を整える
・直接部屋に入るのではなく、リビングなどを経由する配置を考える
家相と精神病についてよくある質問(Q&A)3つ
Q1. 家相が悪いと本当に精神病になるのでしょうか?
A1. 家相だけが直接的な原因で精神病になるとは言い切れません。ただし、光不足や湿気、狭さなどの物理的要因がメンタルに負担をかけるケースはあります。家相を気にしすぎて不安になること自体も、ストレス要因になり得るので注意が必要です。
Q2. 家相が悪いと感じた場合、引っ越しするしかないのでしょうか?
A2. 引っ越しは最終手段です。照明の変更や家具配置の見直し、換気など、今の住まいで改善できるポイントも多くあります。また、観葉植物を置いたり、壁紙を明るい色に替えるだけでも心理的にポジティブな効果が期待できます。
Q3. 風水や家相の専門家に相談すれば解決できますか?
A3. 風水や家相の専門家のアドバイスは、精神的な安心感を得る一助となるかもしれません。しかし、医療的観点からのメンタルケアも必要な場合があるため、強い不安や精神的な不調を感じる際は、心療内科やカウンセラーなどの専門機関への相談も併用することをおすすめします。
まとめパターン
家相が精神面に与える影響は、科学的根拠よりも心理的要素が大きいと考えられます。日当たりや換気、間取りの使い勝手の悪さがストレスとなり、不調を引き起こすことはあるでしょう。
しかし、あまりに「家相が悪い」と思い込むあまり不安を募らせると、その思い込み自体がメンタルに悪影響を与える可能性もあります。
まずは日常的な掃除・換気や、照明・家具の配置替えなど、小さな改善策から取り組むのが大切です。専門家の意見を取り入れることも一つの方法ですが、何よりも自分自身が安心して暮らせる住環境を整える意識が重要です。


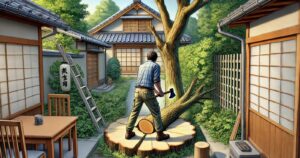




コメント